
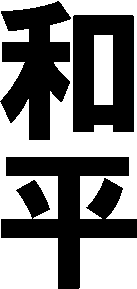 |
||||||
 |
||||||
| *2004年 ■私の聖地■04.12.29 ■シカは食うべきか■04.12.07 ■古事の森への思い■04.08.08 ■微笑みと甘い香り■04.07.22 ■子供たちへの手紙■04.05.07 ■多摩川が好き■04.04.26 ■50歳代の惑い■03.12.25 ■淅江省の魅力■04.4.06 ■「自己責任」糾弾は違う■04.04.20 |
||||||
| ★2006年 ■古代の衣食住現代に伝える■06.12.26 ■椎葉村で考えた■06.11.28 ■すべての大人、手を結べ■06.11.27 ■家族の夢 人の思いを背負って■06.11.15 ■作物は誰が育てたか■06.11.07 ■私の誓願■06.11.07 ■ケニヤからきた象の彫り物■06.10.18 ■ メロンづくりに生きる■06.09.5 ■登山道は即修業道場なのだ■06.08.11 ■知床毘沙門堂例祭■06.07.17 ■人のいる風景を旅する■06.06.15 ■風景は壊れた■06.05.28 ■街づくりに働く■06.05.18 ■ふるさと回帰運動への想い■06.05.12 ■偉大なる自然への畏怖■06.05.10 ■「100万本植樹」掲げ11年■06.05.05 ■身と心で味わう喜び■06.05.03 ■森のいのち■06.04.20 ■一大事が起きるたびに■06.04.14 ■個性を失う地方都市■06.03.30 ■歌声喫茶■06.03.10 ■自然・環境・いのち(1)■06.02.17 ■自然・環境・いのち(2)■06.02.17 ■自然・環境・いのち(3)■06.02.17 ■自然・環境・いのち(4)■06.02.17 |
||||||
| *2001年 ■しみじみと年を取る■01・12/28 ■400年後の楽しみ■01・12/22 ■老後の楽しみ■01・12/12 ■自動車から自転車へ■01・12/9 ■故郷は若いうちにつくる■01・12/5 ■『生命の循環』実感を■01・11/19 ■秋の深まり■01・11/19 ■報復の連鎖断ち切れ!■ ■環境破壊する愚行戦争は絶対やめよ■ ■一言いわせろ■ ■鵜だけを責められぬ■ ■川遊びの楽しさ知って■ |
||||||
| 日光杉並み木を守る配慮を | top |
|
||
|
|
||||
| 足尾の植樹によって私は実に多くのことを学んだ。呼び掛けると、毎年、実にたくさんの人がボランティアの作業にやってきてくれる。 その呼び掛けも、主催者の方で苗や土やスコップ類は用意するものの、できる人はそれらを持ってきてください、カッパや長靴や弁当を持ってきでください、来た人全員から一人千円をいただきますというのである。事務の経費も結構掛かることが理解されていて、多くの人が千円ずつ払ってくれる。世界に誇る「遺産」 私は表土もなくなった山に木を植えながら、田中正造のことを考える。川を治めるには山を治めなければならないと、現代では常織になっていることを、早くから唱えた人物だ。 この治山治水の思想に影響を受け、私たちは足尾に木を植え続けているといってよい。 田中正造の帝国議会での演説記録を読んでいると、江戸時代の人は木を植えて植えまくってきたのに、明治になると切ってばかりではないかと言っている。例えば日光の杉並木も植えた時には小きくても、どんどん育っていき、徳川家の財産が増えていくと同じことだ。あの杉並木は水源にもなっていると、田中正造は言う。 杉並木は本県が世界に誇る先人の遺産である。例幣使街道の杉並木は、今市市に入った途端に始まる。日光神領に入った印で、東照宮の参道を歩いていることを意味する。緑の回 廊である。この街道は日光杉並木が連続して最もよく残っている所だ。 日光に入る街道は三つあり、それぞれに杉並木になっている。宇都宮からは御成街道、会津からは会津西街道である。会津西街道の杉並木はずいぶん消滅してしまったが、御成街道はよく残っている。 杉並木全体で約一万二千本あり、毎年倒れたり、枯れたりして百本前後が失われるという。杉は生き物であるから、死んでいくのはある程度は仕方がない。生き物としての杉には、生きるにふさわしい適地適木というものがある。杉は水を好み、日陰を好む。天然の杉は、谷の底の渓流のほとりなどに多く生えている。 車を降り体感する 御成街道の瀬川辺りは、杉並木が最も元気な所である。よく見れば、杉の列の後ろに農業用水が流れている。昔の人の知恵なのであろう。ところが用水は、コンクリートのU字溝になっていたりする。これでは根に水がいかず、用水はないも同じである。 瀬川の杉並木公園の辺りは、道路は砂利のままで、水がよく浸透するようになっている。今は士を柔らかく保つため、土の中にコンクートのブロックを埋め込む工法などがあり、保存の努力がなされている。 先日、瀬川の杉並木の下を歩いていたら、タクシーが入ってきた。ここは遊歩道だと思ったので、私は静かに注意をした。すると運転手が怒って言う。 「営業車はいいんだ」 客も私の方を怒ったようにして見ている。余計なことをするなということだろう。タクシーは砂ぽこりを上げて杉並木の中に入っていった。 ほかの車もどんどん入っていく。 よく見れば、車が入りにくいようにしてある感じだが、進入禁止とはなっていない。たいした距離ではないし、歩くと気持ちよいのだから、車から降りて杉並水を体感する場所にすればいいのではないか。 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
永平寺にあるはずの雪がない
|
top |
|
||
|
|
||||
| 一月十九日と二十日、越前の永平寺に行った。厳冬期の永平寺は雪のただ中にあると期待して行ったのだが、福井駅に迎えに来てくれたお坊さんは、境内に雪はないと言う。 私は、まさかそんなことはないだろうと思う。なにしろ、真冬の日本海側は深い雪の底にあると、昔から決まっているのである。 福井平野には、はとんど雪らしい雪を見ることはできなかった。遠くにある白山も心なしか雪の色が薄いようにも感じられた。永平寺に近い山の中に入ると、かろうじて日陰に雪がある。正月に寒波が来て、その時に降った雪が、どうにか残っているのだそうだ。 永平寺は道元が開いた寺である。道元が残した有名な歌が、永平寺の山門の石柱に刻まれている。 「春は花 夏はほととぎす 秋は月 冬雪(ふゆゆき)さえて すずしかりけり」 日本の風景の美しさと、自然の流れのごく当たり前の循環について詠んだ歌である。春は花が咲き、夏はほととぎすが鳴いて、秋は月が皓皓(こうこう)と輝き、冬は雪が冴える。この季節の流れは当たり前だから、美しいめぐりなのである。 そうであるはずなのだが、永平寺に雪がない。当たり前の風景が、当たり前ではなくなってしまったのである。これでは道元の歌も、率直には成立しないのであった。 午前四時の永平寺の僧堂は、さすがに底冷えがする。 私たち外来者が座禅をするのは、雲水用のではなく、参禅者用の僧堂で、そんなに寒いとはいえない。それから法要をする法堂(はっとう)に行くと、火の気のない大広間は、さすがに寒かった。それでも、いたたまれないというはどには寒くはない。画廊に出て外を見ると、やっばり雪は物陰にやっ とあるばかりなのである。 暖冬である。今年は十二月には知床に流氷がやってきて、寒い冬になると覚悟していた。一月の初めには寒波が数日続いたものの、暖かい日が連続している。 老師と語り合っていると、二十年ぐらい前には京福電鉄の永平寺駅まで行くのに、寺の門から先は一?以上も雪が積もっていたという。雲水たちがたくさん出て除雪をしてもらわなければ、駅に行くことはできなかったらしい。そうして除雪をして送り出してくれることが、なににもまして心の温かい見送りとなったということである。 私たちの身の回りの実感からいっても、地球は確実に温暖化している。それもすさまじい速度で至・・・・。この流れのままでいると、植物の植生が変わり、食物連鎖の根底が揺らぐことによって、生物の生息環境も大きく変わっていくであろう。もちろん「人間に影響がないはずはない。もしかすると取り戻すことのできない流れになっているかもしれないとも案じられる。 社会新報2002年1月30日(水)
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
森り育て木造建築守ろう
|
top |
|
||
|
|
||||
| 法隆寺で正月にとりおこなわれる金堂修正会(しゅうしょうえ)は、今年で1235回目である。人々が幸福になるように、天下が平安であるようにと、法隆寺では年頭にあたつて祈りつづけてきたのである。その金堂修正会に、承任(じょうじ)と呼ばれる小坊主として出仕するようになってから、私は8年目になった。 厳寒の季節、金堂の片隅で凍えながら声明(しょうみょう)の行いをしつつ、私はいろいろなことを考える。現存する世界最古の木造建築物として法隆寺が残っているのは、それを守ってきた人がいるからである。僧侶の祈りが根本の力となったのはもちろんだが、技術的にこれを守ってきた人がいる。 法隆寺大工と呼ばれた人たちがいつも伽藍を見てまわり、傷んだ個所があるとただちにメンテナンスしてきた。中門の有名なエンタシスの柱も、よく見ればパッチワークのように埋め木がしてある。奈良時代の建物である東大門などは、埋め木の上にまた埋め木が幾重にもしてあり、涙ぐましいような思いにとらわれる。このたえざるメンテナンスの上に、100年から150年に一度は小修理をし、300年から400年に一度は大修理をしてきた。昭和の大修理は、五重塔を解体修理し、金堂の解体中に出火し壁画焼失という惨事を招きつつ、昭和60年に完成した。 法隆寺は、あと300年か400年は大修理の必要はない。400年後に大修理をするとして大きな問題が生じるのではないかと、私は底冷えする金堂の片隅にすわりながら考えた。 現在でも樹齢400年の桧などめったに見られないのに、このまま日本の森が荒廃していったら、古寺を修理する材はまったくなくなるのではないだろうか。伊勢神宮が遷宮のための桧の森を自ら造林しているのは有名な話だが、各寺社でも建物を守るにめの森を自らつくらねばならない時代になったのではないか。 今植えれば、400年後の大修理には間に合うと、私はいつか大修理をしなけ ればならない法隆寺金堂の1400年の闇の中を考えたのである。日本の伝統文化は木造で、森に根ざしている。森が荒廃したのでは、人の精神を未来につないでいくことはできない。 足尾の銅山開発のため表土さえ失われたはげ山の緑化に、私はもう長いことボランティアとして取り組んでいる。そこで知り合った林野庁の人に私の思いをぶつけてみると、話がとんどん進んでいき、国有林に400年不伐の森をつくろうということになった。寺、神社、城郭、橋などに木材を提供する森として、古事の森と名づけよう。 たとえば法隆寺の金堂修正会では、法要に漆の木が必要である。2月の修二会(しゅうにえ)では、赤松の根のジンタと呼ばれる部分でたいまつをつくるのだが、材がない。他の寺社でも、伝統行事に使う特殊木に苦労しているのである。そんな木も供給できる森をこしらえたい。 古事の森は全国につくるのだが、最初に文化財の集中している関西で、一般に広く呼びかけて植林をしよう。森の線引きもはじまっている。今年の4月ごろには、ボランティアへの呼びかけが実現しそうである。 400年たたなければ結果は見えないが、その間、森は多くの恵みをくれるはずである。その恵みは、人の精神に強い影響を与える。
朝日新聞2002年1月27日(日)
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
不況で息の根止められる農業
|
top |
|
||
|
|
||||
| 現在、世間では経済不況の大合唱である。リストラだ、株価が下がった、円が安くなった、企業倒産だと、新聞を読んでもテレビを見ても、この時代の苦しみの声が響いてくる。 当面、自分の生活に影響のない人でも、まるで不安の種を植えつけられたかのように、将来の不安を感じないわけにはいかない。買おうと思ったものでも、伸ばしかけた手を引っ込めて我慢してしまう。 情報過多の時代で、あまりにもその情報が均質なものだから、影響を受けないわけにはいかはい。「情報不況」という言葉さえ浮かんできそうである。 これまでの日本は、ものづくりにこだわり、品質のよいものを外国に売ってきた。一時は、世界中どこへ行っても日本製品にお目にかからないことはなかった。だが、情報や技術が世界に広がり、どこでもものづくりをするようになった。日本だけが独占することはできなくなった。 ひと昔前のことだが、国際分業論という考え方が、まことしやかにまかり通っていた。高度な技術を持った日本はエレクトロニクス製品や自動車を生産し、例えば発展途上の某国では、農業をやればいいというのである。しかし、生産性の悪い農業でどれぐらいコメをつくれば、一台の自動車と釣り合うのであろうか。 国際分業論は、もう一方では、国内の農業を破壊する力として働いた。田んぼをつくるよりは、土建屋になったり、工場に勤めたりしたほうが、現金収入がある。かくして農業はどんどん片手間になり、先祖伝来の土地があるから手放すことはできないという消極的な考えにより、兼業農家がいつしか日本の農業の主流となっていった。 日本の農業を支えているのは、体験的に私が感じるところによれば、土建屋と役場職員と学校の先生ということになる。別の言い方をするなら、ゼネコンと自治労と教職員組合ということになる。 ゼネコソは、この国ではもうつくるべきものも少なくなって、不況である。農村地帯に進出していた工場は、生産拠点が労働賃金の安い中国などに移されていき、空洞化してしまつた。兼業農家を支えていた農業以外の仕事が、頼りにならなくなってきたのである。 こうなったら地方を捨てて東京あたりに出ていくかと、ひと昔前なら考えたろうが、東京に行ってもいい仕事があるわけではない。それなら本腰をいれて農業に取り組むかとなればよいのだが、一度土から離れてしまうと、感覚的にもなかなか土には戻れないものである。 高度成長やバブル経済で農業は踏みにじられ、体力がなくなったところで、不況により息の根を止められる。私にはそんなふうに思えてしようがない。故郷の土さえしっかりしていたら、不況など生き方においてなんでもないことなのだが。 社会新報2001年1月23日(水)
|
|
|||
| 叡智の旅へ |
top |
|
||
|
|
||||
|
地球は美しい。そして、美しい地球と調和して生きる人々は美しいと、この緑なす水の星を歩けば歩くほどに思えてくる。 この地球を動かしているゆるぎのない法則を、真理と呼ぶ。人類はこの真理を知るために悪戦苦闘し、叡智を蓄積して、大文明を築き上げてきたのだ。真理を得ようとする探求心こそが、人類が歴史をつくっていく原動力ではなかったろうか。 だが、東洋の禅思想家はこういう。 「真理は何ひとつ隠されてはいない。私たちのこの前に、すべては明らかになっている。過去は消えてしまったのではなく、未来はいまだ現れないのではなく、すべてが現在の中に現れているのである」 地球の側からすれば、何かしら秘密を保持しておこうということではないであろう。法則に基づいた摂理とは、それぞれの都合をいい立てれば変化するようなものではなく、日々平凡といってよいほどゆるぎなくくり返される不変性のことなのだ。 真理はそこいら中に投げだされているにもかかわらず、私たちにはなかなか見ることができない。それは私たちが本当の叡智を持っていないからである。 欲などに汚されていない澄んだ叡智を持って、果てしのない冒険の旅に出かけていった人が、いつの世にもいたのである。彼はそこいら中にあるはずの真理を辛苦の果てにつかみ、私たちの目の前に示してくれる。 この美しい地球を心から知ったならば、大地や海を少しでも壊したり汚したりしようという気には、ならないはずである。 毎日新聞2002年1月1日(火)
|
|
|||
| 大掃除のごみの行き先をおもう |
top |
|
||
|
|
||||
| 年末になり、私をいれて三名の零細なわが事務所の大掃除をした。本やら雑誌やら資料が山と積まれ、居る場所すらなくなっていた。やむにやまれぬ大掃除であったが、あまりに大量のゴミが出て愕然とした。ほとんどはビニール紐でくくって資源ゴミのほうにまわるのであるが、可燃ゴミになるものも多い。 この十二月、全国で一体どれくらいのゴミがでるのだろうか。整頓された街で新年を迎えるべく、ゴミ収集車が走りまわっている。処理しても処理しても際限もなく湧き上がってくるゴミと、闘っている人がいる。年末あたりに、私は清掃開係者に感謝の気持ちを伝えたい。そして、ゴミを減らす努力もつづけたい。 今年の夏は横浜市下水道局の北部第二下水処理場と北部汚泥処理センターを見学する機会に恵まれ、そこでも下水と終わりのない闘いをする人々の姿を見て感銘を受けた。横浜市民三百四十万人が、休むことなく水を使い、汚して、捨てる。横浜市で直径二十センチから五メートルの下水管の総延長は一万Km以上あり、横浜からシカゴまでいってしまう距離だそうだ。全国となったら、地球を幾回りもするはどの長さになるだろう。 下水処理の仕組みは、まず砂や土を沈澱させ、水に含まれている汚れの素である有機物やリンや窒素は、微生物に食べさせる。つまり、もともとある自然の力を利用するのである。もし化学薬品などを流されると、微生物が死んでしまい、それを回復するのに大変な努力が必要になる。 汚泥処理センターは、卵の形をした巨大なポットが幾つも建ちならび、大規模な施設であった。汚泥を濃縮し、微生物に分解させ、脱水し、焼却して、焼却灰はレンガやセメントの原料とする。 私たちは自分の捨てたものの行き先に、あまりに無自覚である。下水道処理の仕事にたずさわる人にも、年末にあたって感謝の気持ちを捧げたい。 東京新聞2001年12月30日(日)
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
| いつでも書きたくて | top | |||
|
「暗く重い世界で今だって怖い。でも僕らの世代が語り続けていかなければならない」。約30年前、革命を目指した若者たちが仲間14人をリンチで殺害、あさま山荘で警官隊と銃撃戦を演じた連合赤軍事件。革命運動にかかわった同世代は沈黙したままだった。自身も早大の学生時代、運動の周辺にいた。「理想社会をつくることと仲間を殺すこととは絶対に相いれない。あの時代を総括したい」と書き上げたのが小説「光の雨」だった。この作品は長年の仲間である高橋伴明監督が映画化し、今月から公開されている。 宇都宮高から早大政経学部に進学し、21歳のころ小説を書き始めた。身体の奥からあふれてくる何かを表現したかっ。コクヨのB5横書き原稿用紀に縦書きしていくスタイルは今も変わらない。「文学は金や元手がかからない」と思ったが、実際は「『人生の元手』が必要だとだんだん分かってきた」と打ち明ける。 大学を卒業し、日雇い労働などをしながら小説を書き続けた。結婚し翌年に長男が誕生するが、小説は売れず構神的に疲れた。故郷・宇都宮へ戻り市職員となったのが25歳の時。市教委総務課経理係に配属され、市役所から10?離れた団地に住み、自転車で通勤する毎日を過ごした。ある夜、仕事の後に一杯飲んで帰宅する道すがら、誤って自転車ごと川に突っ込んだ。前歯と背骨を折る大けがを負ったが、まず頭に浮かんだのは「これで市役所が休める」。とにかく小説を書き続けたかった。「自分の住む所はここではない」という思いが渦巻いていた。 転機が訪れたのは「だんべえ言葉」と言われる方言で小説を書き始めてから。その文体は栃木が「文化不毛の地」と言われることへの反発でもあった。一連の作品中、「速雷」が野間文芸新人賞を受賞し、注目を集めた。5年あまり動めた市役所は「同じ部署で机がひとつ偉い方へにじり寄った」ところで退職した。 著書は200冊を超え、人気作家として活躍を続ける今、取り組んでいる大きな仕事は歌舞伎の台本。来年3月3日に初日を迎える、坂東三津五郎主演の「道元の月」だ。曹洞宗の開祖・道元が主人公で「因果」をテーマに据える。歌舞伎には年月に磨かれた深みがあり、小説以上に呻吟している。だが「この仕事をやり切らないと作家として生きていけない」との決意で鬪いは続く。 テレビ出演、講演会などの依頼は絶えないが、「まじめな小説家の生活をしないと書けないくらい」の原稿も抱える。とはいえ「いつも書きたくて書きたくて。小説家なんだから当然ですよ」と繰り返す。「来年こそは(書くために)座りたい」。それが今の最大の望みだ。
毎日新聞(栃木版)2001年12月28日(日)
|
|
|||
| しみじみと年を取る |
top |
|
||
|
|
||||
私の生まれ故郷は、栃木県の宇都宮である。その正真正銘の故郷に、死ぬまで付き合える仲間がいる。仲間たちにとっては私はよその土地にでかけて悪戦苦闘しているように見えるのか、冗談まじりでいつでも帰ってこいよといってくれる。 仲間は高校時代の同級生である。私は宇都宮市役所で働いていたこともあるのだが、そこで同僚だった人もいる。職業は農業やら職人やらサラリーマンやら、さまぎまである。人生には浮き沈みがあり、リストラで苦しんでいる人も、会社を倒産させてしまった人も、火事で家が焼けてしまった人もある。私にも何度か人生のピンチがあった。家族の間でも、苦しいことは多いのである。 仲間は高校時代の同級生である。私は宇都宮市役所で働いていたこともあるのだが、そこで同僚だった人もいる。職業は農業やら職人やらサラリーマンやら、さまぎまである。人生には浮き沈みがあり、リストラで苦しんでいる人も、会社を倒産させてしまった人も、火事で家が焼けてしまった人もある。私にも何度か人生のピンチがあった。家族の間でも、苦しいことは多いのである。苦しみも楽しみも分けあおうという仲間である。祝い事があれば、必ずみんなで祝ってきた。子供が小さいころ、夏になればキャンプにいった。その子供たちは大きくなり、自立していくようになった。そうしてもらわなくては困るのだが、親とすれば一抹の悲しみがある。 私が故郷に帰ると、必す仲間が集まる。家族ぐるみの付き合いである。その集まりは俗称「立松和平を囲む会」、略して「ワッカの会」という。みんな女房よりも古い付き会いなのだが、集まりに子供の顔がなくなり、お互いの顔も、また女房ちの顔も、年齢相応にふけてくるのは仕方ない。 仲間の1人が宇都宮郊外の森の中にトレーラ−ハウスをつくったので、正月もそこに集まる。料理と酒を持ち寄り、まわりに気兼ねなく好きなだけ語り合う。コンピューターにたけた人がいて、私のホームページも立ち上げてくれた。 夕暮れは穏やかなほうがよいであろう。私はその仲間とともにしみじみと年を取っていくのである。故郷はあたたかい。
朝日新聞2001年12月26日(水)
|
|
|||
|
400年後の楽しみ
|
top |
|
||
|
|
||||
|
老後の楽しみとして最高なのは、なんといっても木を植えることだ。植えた人間が年を取るのと反比例して、木はどんどん育っていく。私は故郷の仲間たちと「足尾に緑を育てる会」をつくり、鉱山開発のため荒廃し、表土さえも流失してしまった広大なるハゲ山に、6年前からボランティアの植林活動をしている。足尾は母方のでたところだ。子供のころからなじんだ風景である。小説家の私には、「恩寵の谷」など作品の舞台を提供してくれる土地なのである。 足尾銅山は明治政府の富国強兵策の重要な柱で、強引な開発により渡良瀬川の源流域から森林が消滅し、下流一帯に大規模な水と土の汚染を起こした。日本の大規模公害の第1号と呼ばれる、足尾鉱毒事件である。 故郷の古い仲間たちとともに、岩が露出している渡良瀬川源流の山々に、木を植えようと呼びかけた。苗木、土、スコップ、合羽、弁当を持ってきてください、参加費用千円いただきますといら呼びかけにもかかわらず、毎年600人余もの人がきてくれるようになった。 年末に新しい手帳がくると、4月の第4日曜日の欄に、さっそく「足尾植林」と書き入れる。毎年、山は明らかに縁になっていくのが、楽しみだ。 7年前から、私は正月になると、奈良の法隆寺で7日間小坊主をさせてもらっている。自分の勉強のためである。1400年ほども前の世界最古の木造建築を未来へ残していかなければならないのだが、修理しようにも今は桧の良材がない。 法隆寺にかぎらず日本の古寺を守るため、森をつくれないかと本気で考えている。300年か400年不伐の森で、ボランティアの手によってまず植林ができないだろうか。できたら関西あたりの国有林がいい。名づけて「古事の森」である。 400年後の楽しみである。これも元気なうちに始めたい。
朝日新聞2001年12月19日(水)
|
|
|||
|
老後の楽しみ
|
top |
|
||
|
|
||||
|
農園をつくりたいと思った。海と山で学んだその果ての、究極的にたどり着くのは、農園つくりなのである。元気なうちにつくりはじめ、老後に楽しむ。こんな楽しみはない。 そう思ったことの根底には、知床の海や山に通ううち、この自然を後の世にも残しておきたいものだと思うようになったことがある。知床の自然を守っているのは、海ならば漁師、山なら山仕事をする人、大地なら農民だと気ついた。 季節に応じて変化する海のことなら、漁師はなんでも知っている。今、林業が一番弱っているので、森は荒れている。森から湧いた水をうまく使い、大地を耕しているのは、農家だ。 つまり、第1次産業に従事する人が安心して暮らせなければこの国の自然は守れないということだ。私の知床の友人たちは、ほとんどが農家か漁師である。自然の中で働く彼らの暮らしがよくなれば、おのずから知床の自然は守られるのである。 農園をつくろうと、農業法人など模索したのだったが、みんなすでに農家である。その経営基盤を崩さず、その上に有機農業をして、ソバや野菜なとを同じ地域内の観光ホテルに買ってもらう。漁師を中心に魚の加工をし、東京の消費者のもとに届ける。楽しい仕事をしにい。 試行錯誤の末、「知床ジャこ−」という生産者団体を立ち上げたのは、およそ5年前だった。私は創設には力を尽くしたのだが、当地の若い人たちが運営を始めると、手を引いた。 鮭の山漬け、鮭の香草じめ、鮭フレーク、ホタテチップス、ソバ、ジャガイモ等々、知床ジャニーの製品は毎年少しずつ増えてきた。知床にいくたぴ、あれをつくろうと議論し、実現していくのが私には楽しい。 考えてみれば、私の故郷づくりの一つである。老後の楽しみは深い。食べ物だから、どんな時代になろうと強い。私と仲良くしていにほうがいいですぞ。
朝日新聞2001年12月12日(水)
|
|
|||
|
自動車から自転車へ
|
top |
|
||
|
|
||||
|
私は東京都心に近く、首都高速道路の近くに住んでいるのだが、台所の引出しにいれておいた銀のスプーンが、酸化して黒っぽく変色しているのにびっくりする。車の排ガス等の、チッソ酸化物のせいであると思う。 東京の空気の悪さに、改めて驚く。そして、人間の強さにも驚くのである。東京は過密さえ耐えれば、大体が合理的にできた心地よい都市である。ここに空気のよさが加われば、本当に暮らしやすいところになるのだ。 先日、東京都駐車場公社により、「自転車の似あう道」というテーマで論文と作文のコンクールがあった。審査員として呼ばれた私は、東京の空気をよくする切り札は、みんなが自転車に乗ることではないかと思った。 東京で自転車を楽しんでいる人は、意外に多い。それは駅前であふれんばかりに放置されている自転車を見ればわかる。論文にはとにかくこの放置自転車をなんとかすることからはじめなければならないという指摘が多かった。二人来り、逆走、信号無視など、自転車走行のモラルの低さは目に余るのであるが、これは自転車自体が悪いのではもちろんない。人間の問題だ。 通勤に自転車を使えば、電車の混雑も緩和され、空気もよくなり、運動にもなる。よいことずくめである。そのために、乗り捨てのできるステーションをつくり、そこでシャワーを拾び、着替えをし、気象情報も得られるようにしたらどうかという提案もあった。 東京は坂が多い。道路の勾配や標高など徴地形をわかりやすく記載したサイクルマップをつくるとか、水系にあわせた自転車専用道路を整備するとか、さまざまなアイデアによる提案があった。 東京にかぎらず日本の街を、自動車から取り戻す。そんなことを考える時代にきたのだと思うが、現実には道路の拡張やさまざまな工事のため、街はちらかった工事現場のようなのである。 東京新聞2001年12月9日(日)
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
故郷は若いうちにつくる
|
top |
|
||
|
|
||||
|
知床に山小屋を持ったのは、30歳代後半のことだった。あれから15年以上たった。 知床の山にアンテナを建てたかのように、小説家としての情報や滋養をたくさんもらった。友人もたくさんでき、私には第2の故郷のようになった。故郷とはあらかじめあるのではなく、若くて元気なうちにつくるものだと思うしだいである。 今年の冬は、知床の私の山小屋の裏山で映画をつくった。学生時代からの友人の高橋伴明監督が、私の小魂「光の雨」の映画化をしたのである。連合赤軍による粛清事件を描いた、まことにハードな内容なのだ。資金も集まらず監督が苦労していたので、私は場所を提供することを申し出たのである。 知床の仲間たちは、もちろん映画の厳しい内容を知った上で、私がやることだからと全面的に協力してくれた。廃屋なった開拓小屋を壊し、山岳アジトのセットをつくってくれ、運転手もしてくれるし、炊き出しもしてくれ、骨惜しみのない協力をしてくれたのだった。 映画のスタッフも役者も、人情に大いに感じるところがあったとみえる。一般の試写会の第1号を、知床のある北海道の斜里町ですることにした。せめてもの感謝の気持ちを示すため、ホールにはいれる600人を無料招待することにした。町には35?の映写機がないので、16?フィルムをプリントした。 その夜、監督、役者、スタッフ、監督夫人の女優高橋意干さん、もちろん私も、大挙して斜里町の「ゆめホール」にいった。切符は協力してくれた人に要点的に配り、全体では足りなくて大騒ぎだったとのことだ。映画は大好評で、その晩私は東京や知床の友人たちと、うまい酒をたっぷり飲んだのだった。 いつも助けてくれる故郷は、若いうちにつくるものである。50歳を過ぎた私は、そのことを心から思う。老後のために、今すぐ魂の休み場所をつくろう。
朝日新聞2001年12月5日(水)
|
|
|||
|
『生命の循環』実感を
|
top |
|
||
|
|
||||
|
このほど東京都北区立第三岩淵小学校の、環境教育研究発表会にいってきた。この学校の教育がユニークなのは、環境教育を「生きもの」「食」「くらし」に結びつけている点だ。身近にいる生物から、自然に働きかけて食物を得て、それを自分自身の命につなげるという、生命の循環を考えさせる教育を追究している。統一のテーマが「感じ、深め、広げる子ども」である。第三岩淵小学校のある赤羽は完全に都会であるのだが、学校では近くに田んぼを借りて稲を育てている。そのためには土づくりをしなければならない。年毎に収穫量か減ってきたのは、土が疲弊してきたのが原因だと知る。そのためにはどのように土を再生させるかが、子供たちのテーマとなる。 わらもできる。そのわらで縄をなったり、わらじを編んだり、地域の人が先生となって教える。米ができれば、当然料理の仕方を学ばなければならない。食は奥が深くて、追究をすればするほど楽しい。何よりおいしい。 研究発表会の当日、圧巻だったのは、校庭でなされた一年生の授業「わくわくモーモースクール」であった。関東地方の酪農家たちの協力によって本物の乳牛が校庭に連れてこられたのだ。牛は大きくて、なんとなく近寄りがたい。 「みんな冷たい牛乳しか知らないかもしれないけど、牛のお乳にさわってもらおう」 先生にこういわれ、小さな手が恐る恐る牛の大きくて重そうな乳房に触れる。牛乳はどんな牛でもだすのではなく、赤ちゃんを生んだ雌がだす。そんなことも知らない大人が多いに違いない。牛乳をだすメカニズムを子供の時に学べば、一滴の牛乳も無駄にできない大人になる。命の根本を知ることになる。「生きているみんなと仲良くできたらいいと想います」 ひととおりの酪農体験をしてから、一杯ずつ牛乳を飲んだ子供の感想である。
東京新聞2001年11月18日(日)
|
|
|||
|
秋の深まり
|
top |
|
||
|
|
||||
|
北海道では秋は躯け足でやってきて、また駆け足で通り過ぎていく。短い秋の真っ盛りに、私は車で釧路湿原に接する道を走っていた。傾いてきた日差しが、ススキの穂に光のかたまりになって揺れていた。 木の葉も草も枯れさびていく季節なのだが、光が透明な黄金の色に揺れていて、思わず車を止めて外に出た。風は冷たかった。それでも冬の感触とは違い、土のぬくみの香りがかすかに鼻に感じられた。枯れた草に光が宿り、それが風に揺れるたぴ、そのあたりには何人もの美しい天使がいるようにも見えるのだった。私は胸いっぱいに天使を吸い込む。 日か傾いていくにつれ、黄金の光はたちまちあせていき、天使たちは物陰に姿を隠す。あの輝きは人の五感が感じるものであって、カメラでは絶対にとらえることかできない。 秋の深まりゆく時期に、私は知床の奥地の河口に潜水したことかあった。夏の気配の残るころにはカラフトマスが川を真っ黒に盛り上げるほどに遡上(そじょう)していくのだが、カラフトマスの産卵は秋の深まりとともに終了し、次には秋アジと呼ばれるシロサケが大挙して川を遡(さかの ぼ)っていくのである。 雌はイクラで腹をはち切れそうなほど膨らませ、雄は婚姻色で身体を赤く染めて精いっぱい装っていく。赤くなる身体の模様はブナの木肌のようで、この時期の秋アジはフナがかかるといって市場では値段はさがる。栄養分が卵のほうにいき、身に脂分がなくなるからである。もちろんそれは人間の勝手で、秋アジは子孫を残す大仕事に一生懸命なのである。 川を遡りはじめた雌は、精子を提供してくれる美しい雄を見つけ、カップリングをする。雌は自分の腹に卵がすでにあるのだが、雄は卵に精子をかけさせてもらえなければ未来に自分の遣伝子をつないでいくことかできないので、それは必死だ。 カップルができると、底が砂や小砂利でできた流れのゆるいところを見つけ、胸びれやしっぽを使って掘る。産卵がすんだら、二匹は砂や砂利をかけて埋めもどす。魚にとっては重労働であり、身体はばろばろにいたんで、疲労困憊(こんばい)して死を待つばかりになるのだ。 河口に潜っていると、私の下半身は沈んでいるイクラの中に潜ることになる。魚が自分の命と引き換えに産んだ卵は、後からきた秋アジが掘り返してまた産卵をするので、水に流れだしてしまう。川底を無数のピンポン球のように弾みながら流れ落ちてくるのだ。それが流れのゆるい河口に一?もの深さで沈む。 私の水中マスクのガラスに、半分がい骨になった秋アジが、恐れるものは何もなくなったかのようにちょんちょんと軽く口をぷつけてくる。腹に穴があき、内蔵が流れでて空っぽになった魚がいる。しつぽか腐ってなくなり、背骨をむきだしにして泳いでいる魚がいる。死んだと思って横になっている魚に触れると、ゆらりと起き上がって泳ぎだす。魚は自殺しないのだなと、私は改めて知る。未来に命を投げる大仕事をすませた魚たちは、ゆっくりと迫りくる死を待っている。 ぽうぜんとしてながめる私をかすめ、これから産卵に向かう魚か風を立てるように勢いよく水を揺らせ、群をなして遡上していく。少し多く雨が降ると、すべては沖に流され、別の魚やプランクトンのえさになる。自然界に無駄はない。 秋は生と死とが交差するすさまじい季節である。
熊本日日新聞・共同通信2001年11月13日(火)
|
|
|||
| 「報復の連鎖断ち切れ!」 | top |
|
||
|
|
||||
|
同時多発テロのアメリカ軍による報復として激しい空爆がおこなわれ、ついに地上軍が投入された。当たり前の暮らしをしていた普通の人が殺害 され、あるいは逃げて難民となり、苦難の時を過ごしている。このことで私にはどうしてもいいたいことがあり、またしてもペンをとったしだいである。 この欄は環境問題について書くところであるのだが、森の存亡に関して、戦争は地球環境にとって最悪である。爆発物を大量に使うので二酸化炭素を大量に発生させ、地球温暖化に大きな影響を与えるというのは、わかりやすいことである。 だが、それ以上に深刻なのは、人の心を荒廃させることだ。すべては心が命じるのだから、どんなことをしても心に痛みを 感じなくなる。そうなれば、地球はますます荒廃していかざるを得ない。そもそも地球への愛がなくて、どうして環境問題を説けるのか。 私は「発句経(ダンマバグ)」の中村元先生翻訳の一節を、何度でも引用する。 「実にこの世においては、怨みに報いるに怨みを以てしたならば、ついに怨みの息むことがない。怨みをすててこそ息む。これは永久の真理である」 報復に報復をもってすれば、報復の連鎖が果てしなくつづいていくばかりである。本稿を書いている二〇〇一年十月二十四日(水)の東京新聞夕刊の一面トップの見出しは、「ホワイトハウス施設で炭疽(たんそ)菌」である。 アフガニスタンのタリバン政権に報復するアメリカ軍は、圧倒的な火力を持っている。しかし、戦いでいつも象が勝つとはかぎらない。蟻一匹で、堤防も決壊するのだ。私 はテロという暴力を容認はしないが、歴史的に冷静に見ると、追い詰められた弱者が最後の手段として使うのがテロなのである。たとえタリバン政権を崩壊させたとしても、激しい怨みが残り、報復は消えることはない。炭疽菌などという隠微なテロは隠然とつづく。 美しい地球を残すためには、人の心も清浄でなければならず、そうするためには報復の連鎖を断つことだ。殺し合いはいけない。
東京新聞2001年10月28日(日)
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
環境破壊する愚行戦争は絶対やめよ
|
top |
|
||
|
|
||||
|
アメリカの同時多発テロは、環境問題から見れば最悪の事態である。ニューヨークのウールド・トレード・センターのゴミになった残骸の山を見るにつけ、ヒリヒリと地球が傷む音が聞こえる感じがする。この残骸の中には、死体がたくさんあるのだ。 それに対するに、アメリカ大統領は即座に復讐を決意し、アメリカ国民の大多数が支持して、主犯と目されるビンラディン氏をかくまうアフガニスタンのタリパン政権と戦争がはじまる気配である。日本政府はアメリカ政府に盲従し、たいした議論もなく日本も戦争に巻き込まれそうだ。新聞やテレビは攻撃はいつかと好戦的な気分をあおっている。はっきりと、私は言おう。私は戦争することに反対である。人が六千人以上も殺されたから、敵と目される人々をもっと殺そうという発想が恐ろしい。怨みに対するに怨みをぶつけ、その怨みを解消しようというのだが、憎悪はますます燃え上がり、死者が増えていくだけだ。罪のない人を死に巻き込む戦争より、テロの犯人を裁くのが民主主義ではないか。 この原稿を書くため、私は都営パスに乗って家に帰ってきた。大型パスは走行中は電気自動車になるハイブリッドで、信号で止められれば運転手はエンジンを切る。二酸化炭素の排出量をおさえ、地球温暖化をほんのわずかでも防止するためである。 環境にやさしい生活とは、つまるところ節約である。赤信号のたぴエンジンを切るみみっちい行為を嘲笑するかのように、盛大に火器を撃ち、爆弾を爆発させ、ガソリンを湯水のごとく消費し、ミサイルを放つ。環境を守ろうというささやかな人の行為は、いとも簡単に踏みにじられる。そして、後に残るのは人間の無数の死体なのである。それがまた憎悪を呼び、憎悪の連鎖は果てもなく、すべてが地球環境破壊につながっていく。 地球環境を守るためにも、戦争という愚行はやめよう。殺すな、壊すなと言いたい。
東京新聞 2001年10月7日
|
|
|||
| 殺 す な | top |
|
||
|
|
||||
|
はっきりいおう。いかなる理由があれ、私は戦争に反対である。過去のどんな戦争の場合でも、公然たる理由があった。大多数が賛成して、正義の名のもとに 酸鼻の戦争が行われたのだ。 ニューヨークのワールド・トレード・センターでのテロはごく一般の市民を見境なく殺戮(さつりく)したという点でも許されるべきではないが、それに対し復讐(ふくしゅう)すべきだとマスコミを先導にして世論は一致し、異論を挟めるような状況ではない。みんなのぽせていて、そのことが恐ろしい。西部劇で殺人者をみんなで寄ってたかって私刑(リンチ)にし、しばり首にするようなものではないか。 犯罪者はルールの上で裁くというのが、民主主義ではないのか。世界観を異にする異教徒なら殺してもよいとお互いに心の底で思っていることが、無差別テロと復讐としての戦争とになるのであろう。 「これは戦争だ」 「この難局にあたって…」 テレビで耳に挟んだ、アメリカと日本の指導者の言葉である。完全に戦争を決意した言葉ではないか。こんな言葉をすんなり受け入れてしまう時代が恐ろしいのだ。 キリスト教でもイスラム教でもない、仏教の側から一言いおう。「発句教(ダンマパダ)」の言葉である。 「実にこの世においては、怨(うら)みに報いるに怨みを以てしたならば、ついに怨みの息(や)むことがない。怨みをすててこそ息む。これは永遠の真理である」 (中村元訳) 戦争が起これば、まに多くの人が死ぬのだ。憎悪の連鎖は際限もなく増幅していく。
スポーツ報知2001年9月30日
|
|
|||
|
鵜だけを責められぬ
|
top |
|
||
|
|
||||
|
故郷の宇都宮に帰った時、これはどうしても書いておいてくれといわれたことがある。その友人は夏になれば鮎釣りをし、それが何よりの楽しみだというのである。披の主な釣り場は鬼怒川である。ところがこの数年、釣果はさっぱりだという。彼のいい分を聞いてみよう。 「朝、夜が明けて間もない頃、鵜が空を真黒に染めるほどにやってくるんだかんね。川鵜だか海鵜だかわかんないけど、カラスじゃない。そのへんの雑木林に泊まって、明るくなる頃に鬼怒川に何万匹と集まって、放流した鮎の稚魚を全 部食べちゃうんだ。ど−しようもないよ。どの鵜の胃の中にも、何十匹って鮎の稚魚がはいってんだんべ。しかも、毎日だから。これじゃ釣れなくなっちゃうべえ」 早口で私は訴えられる。日本の川はほとんど漁業協同組合がアユやイワナやヤマメを放流し、釣人は入漁料を払って川に糸を垂れる仕組みである。年間の入漁料ともなれば、結構な金額になる。一年間の遊びの経費だと考えればそれほど高 いとも思わないのだろうか、釣れなければ金を返してくれというような気分にもなるだろう。 「鬼怒川は東京からも近いし、釣人がたくさん集まるところだったけど、鮎が鵜に食べられて全然釣れないんだかんね。釣人がこなくなったから、漁協だって大変だんべ」 ここのところ、日本のあっちこっちの川で鵜の被害が発生している。鵜か憎いとばかり」川堤に立てた棒に鵜の死骸をつるしてあるのを、私は何度か目撃しているのだ。鵜は保護鳥だで殺してはいけないはずだ。 鵜にすればもちろん原因があるから、これまでこなかった川にやってきて、魚を食べまくっているのだ。海辺が開発されて荒廃し、鵜は棲家を追われたのかもしれない。 この出来事も、自然の上げる悲鳴なのである。川の生態系も大きく変わっていけば、釣人の楽しみを奪ったというだけではすまなくなるのである。
東京新聞2001年9月16日
|
|
|||
|
川遊びの楽しさ知って
|
top |
|
||
|
|
||||
|
四国の川にいってきた。アユ釣りの名所であり、豊かな自然がたっぶり残っている日本屈指の大河、吉野川である。ここで開かれた「川の学校」第一期吉野川・川ガキ養成講座に、私は講師として招かれたのだ。 川の学校はカヌーイストであり作家である野田知佑さんを校長に、吉野川シンポジウム実行委員会が主催する。一年間で一泊から二泊のキャンプが五回、吉野川の源流から河口まででおこなわれる。参加者は小学校五年生から中学校三年生までで、この全部のキャンプに参加しなければならず、親の付き添いは認められない。三十名定員のところ、二百名以上の申し込みがあり、抽選で決めた。 私がいったのは、第三回目の八月のキャンプで、吉野川上流の支流である租谷川であった。山また山の過疎の村で、村 人が離村する時田んぼに杉を植えていった。山道を子供たちと歩いていると、石垣のある棚田の形をした杉林がある。そんな悲しい時の流れも、子供たちは学んでいく。 川ガキとは、川で遊ぶ子供という意味だ。夏の川にいっても、昔と違って川で遊ぶ子供の婆を見ることはめったになくなった。子供たちが心身ともに川で遊ぶ機会は失われ、そのことでどれほど悪い影響があるのかと、私は心痛く思うのである。 ニッポン川ガキは絶滅危惧種だ。これは川が汚れ、大人たちが子供たちを川で遊ばせておく心の広さを持たず、つまるところ川ガキの生息環境が失われたのである。 近頃の子供たちは、簡単な道具で魚を釣る方法も知らず、川で泳いだこともない。これでは自然を大切にしようという気持ちは養うことはできない。そこでかつての川ガキであり、川の楽しさを身に染みて知っている大人たちが集まり、川の素晴らしさを子供たちに教え、自分たちも楽しもうというのである。 川にはいるや、子供たちはたちまち輝きだす。 そのことを見ているのか私には楽しい。
東京新聞2001年8月26日
|
|
|||