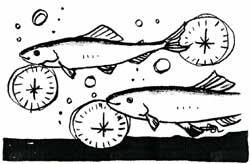いかがお過ごしですか。この移ろいやすい世の中で、子供の君たちが何を考え、どのように生きようとしているのか、もしくは何も考えないようにしているのかと、すでに五十六年もこの世に生きた私は考えてしまいます。世代の間でものの考え方にどんどん開きができているようで、正直いって私は不安を禁じえません。
世代間のことだけではありません。地域によって、住んでいる環境によって、ものの考え方とらえ方がますます隔っていくようで、これだけ通信網が発達した時代にあって、むしろ心の交流が疎外されているような気がしてなりません。
心の交流が疎外されていく究極の行き方は戦争でしょうが、この地球上で戦争が現実に起きているのです。しかもいとも簡単に起こってしまい、ミサイル攻撃をするシーンが、あくまでも発射する側のポジションでですが、テレビで見られたりするのです。爆発した炎の下でたくさんの人が死んでいるのに、テレビ画面の中に写しだされる映像はまさにコンピューター・ゲームのようで、血のにおいはまったくしないのです。
しかしそのように安閑としていられるのも、テレビ画面のこちら側にいるからで、向こう側にいたとしたら、恐ろしくてどうしていいかわからなくなるでしょう。ミサイルが頭の上に落ちてきたというそれだけのことで、人は死ななければなりません。その国に生まれたから、その地域に生まれたからというだけで、たった一つきりの命を捨てることができますか。
知らないうちに画面の向こう側に、攻撃を受ける側に立っているのが、今日の私たちの姿なのです。あくまでも知らないうちなので、攻撃されてからはじめて自分の立っているポジションを知るといった具合なのですよ。たぶん、もう、私たちはミサイルの弾頭の下にいるのです。私たちが望んだことでは、絶対にないのに。
一度だけ、私は爆撃される側にまわったことがあります。テレビの取材で、内戦中のレバノンにはいり、イスラム・ゲリラの基地に泊まり込んでいました。ごく単純化してしまえばイスラム教徒とキリスト教徒の内戦で、私たちがはいった時には各国の大使館も通信社もすべてが国外に
脱出していました。そんな時に報道機関としてはいったものですから、まあ私たちは歓迎されたわけです。
戦時下の日常生活をレポートするのが私たちの仕事でした。しかし、もともと同じ大地で共存していた彼らが何故いがみ合い、殺し合いをするのか、情報としては知っていても、本当のところはまったくわかりませんでした。苦労して現場にいってみると、確かに戦争がありました。ロケット砲や迫撃砲やマシンガンを撃ち合い、殺し合いをしていました。戦場にいる兵士たちにはもちろん彼らにしかわからない恐怖はあったでしょうが、それ以上に激しい宿命というものがあり、それに基づく正義というものがありました。家族を守る、故郷を守るという以上の正義はありません。実際に彼らは家族を殺され、土地を奪われ、多くの犠牲者をだして土地を取り返しても、オリーブの樹の下には地雷が埋められていました。それでまた何人もが殺されるのです。
彼らには戦う理由がありましたが、その姿をリポートしにいった私たちには、好奇心や仕事やらは確かにありましたが、自分が死んでもいいと納得できる正義はまったくありませんでした。
もちろん誰にも銃口を向ける理由がない私たちは、カメラとペンしか持っていませんでした。
イスラム・ゲリラの基地に泊めてもらった時のことです。もともとそこは大金持の別荘で、四階建てでした。四階は砲撃されたら危険なので、使いません。一階も白兵戦で攻撃を受けやすいので、土嚢が積んであるばかりで、人ほ使っていません。二階が兵士たちの留住区で、私たちは三階を使ってよいといわれました。マットレスと毛布を一枚ずつ渡されたのですか、戦場に慣れている人は安全な場所にさっさとマットレスを敷いてしまいます。私はもたもたしてしまって、せめて頭だけは柱の陰にはいれるようなところで眠ることにしました。
その晩、迫撃砲の攻撃を受けたのですが、あんなに恐ろしいことはありませんでした。敵がどこにいるかわからないのに、私は攻撃をされているのです。ある陣営の側に泊まったために、敵の陣営からは私たちは敵になっているのです。私たちには信念などありませんでしたが、明確な敵になってしまったのでした。
迫撃砲の攻撃は正確ではないので、いつどこから弾が飛んでくるかわかりません。近くに着弾すると、地面とまわりの空気かビリビリと震えます。私たちはといえばカメラやペンを握りしめ、暗闇の底にはいつくばって、じつとしているほかありません。
私は恐怖のためにどうしていいかわかりませんでした。私は憎悪にさらされている自分を感じたからです。それがどのような理由で、どのような過程をへてつくられた憎悪なのかわからないのですが、ただ恐ろしい憎悪の現実だけがそこにありました。しかも、私はその底なしの憎悪を、無力で、沈黙して、もっぱら受けとめているしかありませんでした。敵を無差別に殺してしまおうという憎悪ほど、恐ろしいものはありません。その時に、私は、戦争というものがほんの少しわかったような気がしました。
少し冷静になった私は、迫撃砲の発射音と、着弾する爆発音との関係を感じはじめていました。発射音がして、秒数を数えはじめ、一、二、で爆発するのは敵から近いところが狙われています。
弾がだんだん近づいてきて、一、二、三、でちょうど私のいるところに落ちます。その時には生きた心地はしませんでした。日本に残してきた家族のことを考え、なぜこんな仕事を受けてしまったのだろうと後悔しました。しかし、どう考えようと、どう後悔しょうと、爆発する弾の近くに私がいるのだという事実はどうにもなりませんでした。もし爆弾を受けて死んでしまったら、私の人生はここでサヨナラです。なんとつまらない生涯を送ってしまったかと、私ばかりでなく、誰もが思うでしょう。私は戦死でもなく、ただの犬死です。あのすさまじい憎悪を感じただけで、私はそのまま死んでしまいそうになったのでした。
そのうち、一、二、三、四、と数えられるようになりました。弾はそれていき、攻撃目標が変わったことがわかったのです。しかし、再度攻撃目標が変わるかもしれず、マットレスにうつぶせにしがみついている同じ姿勢で、神経だけが張りつめていました。
明け方に、ほんの少し眠り、外で人が騒ぐ声で目覚めました。エンジンの音が聞こえたので窓(もちろんガラスははいっていません)からのぞくと、兵士たちが小さな戦車を乗りまわしていたのです。戦闘があって、そのぷんどり品だったのでしょう。そこでも何人か死んだのに違いありません。
レバノンではその後も何度か命が危いこともありましたが、私たちは無事に日本に帰ってきました。平穏な日常生活に戻り、もう二十年もたつのですが、時々私はあの憎悪を思い出します。この文章を書いていて、また思い出したのです。思い出しただけで、身の毛がよだちます。しかも、私が全身で感じた見も知らぬ人からの憎悪が増幅されて、この時代を覆っているようにも思えてくるのです。
私が感じたあの憎悪の濃度を何万倍にも煮詰めて、しかも長時間、生涯の間感じている人が、今日の地球にはたくさんいるに違いありません。なんと恐ろしい人生なのでしょうか。戦争とは、あの憎悪のことです。
電子戦争になって、敵の姿もわからないのに、あの憎悪だけはまざまざと感じているに違いない。憎悪だけか人間的な感情だとでもいうかのようにです。人が現実的に生きて死ぬという局面には、思想の問題を通過していくにせよ、最後には感情の問題しか残らないのではないでしょうか。死ねば、人間は血まみれの肉になってしまうのです。その人が何を考え、何を学び、どんな家族を持ち、どんな人生を送ってきたのかなど、戦場では、まったく関係ありません。しかも市民生活の場が戦場なのです。
戦場にある感情とは、何度もいいますが、ただ憎悪だけです。
そんな生き方死に方を私はしたくない。また子供たちにもしてほしくない。君たちには他人に対して憎悪などという感情を持ってほしくないというのが、ささやかな体験をしてきた私の、本当にささやかな願いです。
憎悪というのは、すぐ隣りにいる人への感情からはじまるのです。教室で机をならべているクラスメートへのささやかな感情のもつれから、いじめに発展していきます。間はとばしますが、隣りの人を憎いと思う感情が、ずっと増幅していって大きくなり、究極の先には戟争とつながっているのです。そこまでは一見して遠いようなのですが、キイボードーつ押せばよいゲームなのだとしたら、その距離は案外に近いかもしれないのです。
自分と違う人間を認めなければならない。違うからこそ付き合っているとこちらの世界もひろがるのだし、楽しいのだ。私はそのように思っています。他人を認めるためには、寛容の心がなければなりません。許し合う心といったらいいかもしれません。
人間は感情の動物なので、憎悪に凝り固まってしまったのでは、なかなか寛容の気持のところに戻っていくことはできません。そこまでいかないようにしなければならないのです。
ではどうしたらよいのか。私にはいつも身近に置いておく書物があります。二ページでも三ページでも読むと、心の中が清らかになったような気がしてきます。プッダが直接人々に語った言葉に最も近いとされる原始仏典の 「ダンマバグ(法句経)」で、私の尊敬する故中村元先生が原典のパーリ語から直接訳されています。
三「かれは、われを罵った。かれは、われを害した。かれは、われにうち勝った。かれは、われから強奪した。」という思いをいだく人には、怨みはついに息(や)むことがない。
五 実にこの世においては、怨みに報いるに怨みを以ってしたならば、ついに怨みの息むことがない。怨みをすててこそ息む。これほ永遠の真理である。
二千五百年も前に生きたプッダの言葉をこうして味わってみると、人間というものはまったく変わっていないと思ってしまいます。怨みが怨みを呼ぶので、争い事の解決には、怨みを捨てるしかないのです。そのためには、相手のことを理解する寛容の心がなけれぱいけません。困難なのですが、そうできるよう少しでも努力しなければいけないということです。
また「ダンマパダ」にはこのような言葉もあります。
「一二九 すべての者は暴力におぴえ、すべての者は死をおそれる。己か身にひきくらべて、殺してはならぬ。殺さしめてはならぬ。」
こんな言葉を噛みしめて、君たちにはおおらかに生きていってほしいと思います。経済も含めて社会の競争は苛烈で落ちこぼれたものは抹殺されるような時代なのですが、だからこそ、君たちには人への慈しみを忘れないでほしい。少しずつでもいいですから、そんな生き方をつらぬいていってほしいと願っています。
では、また会いましょう。会って、時代のこと、心のこと、いろいろ語り合いたいと思います。
「それでも私は戦争に反対します。」
日本ペングラブ編
平凡社 2003年3月
|
|
|