 |
魂の置き場所 |
||||||
後記
|
|||||||
初版発行:2007年11月30日
|
|||||||
戻る |
|||||||
 |
南極で考えたこと |
||||||
☆はじめに − 南極の旅へ
|
|||||||
初版発行:2007年11月30日
|
|||||||
戻る |
|||||||
 |
伝統工芸、女性の匠たち織る、染める、焼く・…‥至宝12人の「技」と「生き方」 |
||||||
◎まえがき
|
|||||||
初版発行:2007年10月30日
|
|||||||
戻る |
|||||||
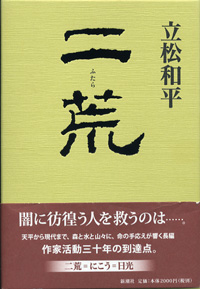 |
二荒 |
||||||
|
|
|||||||
初版発行:2007年9月25日
|
|||||||
戻る |
|||||||
道元禅師
|
道元禅師
|
||||||||||
 |
一 清盛入道
|
 |
十六 大宰府
|
||||||||
初版発行:平成19年7月25日
|
初版発行:平成19年7月25日
|
||||||||||
あとがき - 道元禅師の御生涯を書く
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
戦後民主主義教育で、人間は平等だと教わった。勉強が出来るやつも出来ないやつも平等だと。では、なぜ勉強しなければならないのか、と疑問に思った。
|
|||||||||||
戻る |
|||||||||||
 |
晩 年 |
|||||
後記 「三田文学」編集長加藤宗哉氏とは、不思議な縁がある。お互いに学部の学生の時代は終っていたが、終って間もなくの頃である。加藤氏は「三田文学」に小説を発表し、私は「早稲田文学」を舞台として創作活動をしていた。お互いにライバル視するところがあり、加藤氏がよい作品を発表すると、すかさず私も読んで、闘志を燃やして新たな作品に向かっていったものだ。三十五年以上も前のことである。私たちには文学の青春時代といったところであったのだ。 あれから幾星霜をへて、「三田文学」編集長になった加藤氏から短篇小説を書かないかといわれた時、私には過ぎ去った時というものが整ってきたのである。思いをこらしてみれば、消えていった時の中で同様に消えていった数々の人がいる。私の中に生きている人々は、私がその人のことを忘れてしまうと、少なくとも私が支えていた分だけの存在が消滅する。そのことを痛みのような感覚として感じたのである。
|
||||||
初版発行:2007年6月6日
|
||||||
戻る |
||||||
 |
知床の四季を歩く |
|||||
あとがきにかえて ヒグマと暮らす奇跡の空間 知床は野生の生態系がよく残っているところである。知床半島の奥地にいくと、ヒグマが数多く生息している。野生のヒグマを見ることは、それほど困難ではない。ここに知床の特異性があるのだが、そこには漁師たちが定置網の漁業を営む番屋があって、無人の大自然というのではない。
|
||||||
初版発行:2007年5月31日
|
||||||
戻る |
||||||
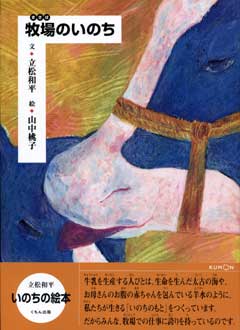 |
まきば
|
|||||
初版発行:2007年3月12日
|
||||||
戻る |
||||||
 |
大洪水の記憶木曽三川とともに生きた人々 |
|||||
おわりに ー 伊勢、裏木曽、木曽三川、そして志摩の海へ
|
||||||
初版発行:2007年2月20日
|
||||||
戻る |
||||||
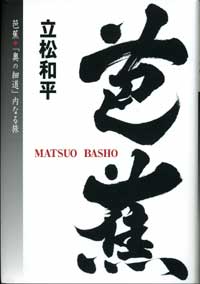 |
芭 蕉「奥の細道」内なる旅 |
||||
後 記
|
|||||
初版第1刷発行:平成19年1月30日
|
|||||
戻る |
|||||
 |
地球の息 |
|||||
後記
|
||||||
初版発行:2006年12月31日
|
||||||
戻る |
||||||
 敗戦国である日本は、飢餓の恐怖からはおおむね立ち直ったものの、戦後一〇年以上たっても深い傷が癒えないでいた。国際社会で日本は孤児であり、人々は自信を持てないでいたのだ。そんな時、日本が国際舞台に復帰し、日本人に自信を持たせるべく試みられたのが南極観測なのであった。
敗戦国である日本は、飢餓の恐怖からはおおむね立ち直ったものの、戦後一〇年以上たっても深い傷が癒えないでいた。国際社会で日本は孤児であり、人々は自信を持てないでいたのだ。そんな時、日本が国際舞台に復帰し、日本人に自信を持たせるべく試みられたのが南極観測なのであった。 唯一、上陸可能な東オングル島に昭和基地を建設したのは、昭和三二(一九五七)年一月二九日で、それから五〇年たった。最初の昭和基地は壁パネルを組み合わせて建てる日本初のプレハブが四棟で、日本建築学会の工夫である。
唯一、上陸可能な東オングル島に昭和基地を建設したのは、昭和三二(一九五七)年一月二九日で、それから五〇年たった。最初の昭和基地は壁パネルを組み合わせて建てる日本初のプレハブが四棟で、日本建築学会の工夫である。 だが冷戦下の旧ソ連の砕氷船「オビ号」が救援に駆けつけてくれ、「宗谷」は無事に脱出することができた。そんな感動のシーンを私が鮮明に覚えているのは、学校で授業の一環として映画館に連れていかれて観た記録映画のおかげである。当時小学生より上だった世代は、誰でも知っている話である。
だが冷戦下の旧ソ連の砕氷船「オビ号」が救援に駆けつけてくれ、「宗谷」は無事に脱出することができた。そんな感動のシーンを私が鮮明に覚えているのは、学校で授業の一環として映画館に連れていかれて観た記録映画のおかげである。当時小学生より上だった世代は、誰でも知っている話である。