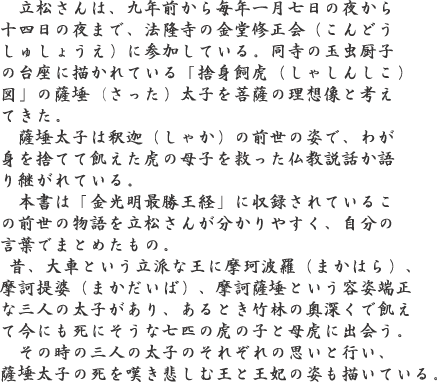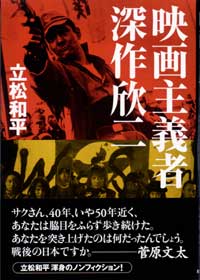あとがき
その昔、私が二十代前半のことである。私は身寵(ごも)った妻を東京に残し、一人でインドに旅立ったことがある。そのことを書いたり語ったりしているものだから、何故そんなことをしたのかと、今でも私はよく人に問われる。言下には、ひどい男じゃないかという意味が込められている。私もそう思う。いかにも弁明のしようもないことである。
その旅で、私は中村元先生の翻訳された『ブッダのことば__スッタニパータ』 の文庫本一冊を持っていった。いつも荷物を担いでいなければならないバッグパッカーだから、何度も読める本がよい。書店の書架から深い考えもなしに取りだしたのが、この原始仏典だった。これからインドにいくのだし、雰囲気に合っているなというくらいの軽い気持ちであった。
朝日覚めた安宿のベッドで、南京虫に喰われた痺い腕を掻きながら、私は文庫本のページを繰る。街の食堂でカレーを注文し、運ばれてくるのを待ちながら、カレーの染みのついたテーブルに 『ブッタのことば』をひろげる。
その時に印をつけた言葉はこのようなところである。
あらゆる生きものに対して暴力を加えることなく、あらゆる生きもののいずれをも悩ますことなく、また子を欲するなかれ。況んや朋友をや。犀(さい)の角のようにただ独り歩め。
〈三五)
交わりをしたならば愛情が生ずる。愛情にしたがってこの苦しみが起る。愛情から禍いの生ずることを観察して、犀の角のようにただ独り歩め。
(三六)
あらゆる生きものに害を加えずに生きることは、日々をそのように願って時を過ごせば、あるいはできるかもしれない。しかし、私にはもう一つの現実があった。愛情の結果、子ができようとしていたのだ。その子を受けいれられるような生活をしていない以上、それは苦しみである。だが禍いなのであろうか。ブッダはあらゆる執着を捨ててしまえば、生きる苦しみはなくなるといっている。確かにブッダは、親も妻も子も家も捨てた。私はブッダがしたようにはとてもすることができない。
何気なく持っていったたった一冊が私の苦しみをずばりとついていた。しかし、簡単に答えがだせるようなことであるはずがない。私は一冊の文庫本と対話をするような旅をつづけることになった。迷いは深くなるばかりではあったが、私は妻のもとに帰っていった。その時に生まれた子は私と妻とに幸福な気持ちをもたらしながら育っていき、成人し、そして自分の道へと去っていった。気がつくと三十年の歳月が流れたのである。
諸行無常でいろいろなものは当然変わったのだが、一つ変わらないことは、いまだに私はあの文庫本を読みつづけているということだ。南京虫(なんきんむし)の巣窟である安宿のベッドも、カレーしかない雑踏の食堂も、私のまわりからは遠い。しかし、あの時には遠かったブッダの言葉は、今は私自身の心の中から響いてくる。
あの時、私の深いところに蒔かれた種が芽をだし、少しずつ少しずつ樹になってきた。それが大樹になるかどうかは私の精進にかかっているのだが、確かに種は蒔かれたのだということを感じる。種は一種類ではなく、苔も羊歯も草も、また幾種類もの樹木もあるようだ。生きているうちにその種類は増えていく。
これが森にまで育っていけばいいなあと、私は念じている。
|