|
那須野とは、西那須、大田原、黒羽のあたりである。日光北街道の大田原から黒羽に近づくところに、箒川にかかる橋がある。名づけてかさね橋という。橋のたもとには自然石の稗が立ち、馬上の松尾芭蕉と、供の曽良と、そのあとから追ってくる二人の子供の金属レリーフ板がはめ込まれている。
「おくの細道」の那須野の部分を意訳してみよう。
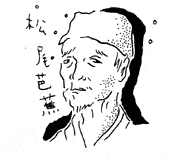 那須の黒羽というところに知り合いがいるので、これより本街道をはずれて那須野を越え、まっすぐな近道をいくことにした。遠くの村をめあてにいくうちに、雨が降り、日が暮れてきた。農家に一夜の宿を借り、夜が明けたらまた一面の野の中をいく、そこここに放牧の馬がいる。草を刈っている男に頼み込むと、田舎のものといってもさすがに情も知らないのではない。 那須の黒羽というところに知り合いがいるので、これより本街道をはずれて那須野を越え、まっすぐな近道をいくことにした。遠くの村をめあてにいくうちに、雨が降り、日が暮れてきた。農家に一夜の宿を借り、夜が明けたらまた一面の野の中をいく、そこここに放牧の馬がいる。草を刈っている男に頼み込むと、田舎のものといってもさすがに情も知らないのではない。
「さて、どうしたものでございましょう。この野の道は道が縦横に分かれ、はじめての旅人はまちがえましょう。そうなるのも心配ですから、この馬に乗っていって、馬が止まったところでこの馬をお返しください」
こういって馬を借してくれた。小さな子供が二人、馬のあとを追って駆けてくる。一人は小娘で、名を聞いてみると「かさね」という。開き慣れない名が優雅に感じられたので、
かさねとは八重撫子(やえなでしこ)の名なるべし
曽良
やがて人里に至ったので、代金を鞍に結びつけて馬を返した。
なんと美しいエピソードであろうか。「かさねとは‥」の句のおおよその意味は、こんなふうである。
かわいらしい子供を撫子にたとえるが、この子はひときわ美しい八重撫子であろう。
この文章からは、那須野は馬が放牧されていた草の海のようなところだったとわかる。その中に細道が縦横に走り、複雑に分かれていたのだ。もちろん今はよく開けた田園地帯で、草茫々というわけではない。古老に尋ねると、萱刈り場は相当な面積があったということである。萱屋根の材料をとるための村の共有地で、もしかすると芭蕉と曽良はそこに迷い込んだのかもしれない。
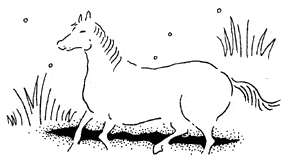 この草の海に迷った見ず知らずの旅人に、農夫は馬を貸してくれた。そんなことはあり得ないとして「おくの細道」を華やかに彩るための芭蕉のフィクションであろうという研究者は多い。フィクションかノンフィクションか調べようもないのだが、私は本当にあったことだと思いたい。大田原や黒羽のあたりを旅すればわかるのだが、そのあたりに住む人は大体人がよくて、そのうちの何割かは底ぬけにお人よしだ。見知らぬ巡礼風の旅人に貫重な財産の馬を貸そうものだろう。曽良の随行日記にもこのエピソードは書かれていない。だからといって芭蕉のつくり話だといってしまうには、あまりにも自然な物語である。 この草の海に迷った見ず知らずの旅人に、農夫は馬を貸してくれた。そんなことはあり得ないとして「おくの細道」を華やかに彩るための芭蕉のフィクションであろうという研究者は多い。フィクションかノンフィクションか調べようもないのだが、私は本当にあったことだと思いたい。大田原や黒羽のあたりを旅すればわかるのだが、そのあたりに住む人は大体人がよくて、そのうちの何割かは底ぬけにお人よしだ。見知らぬ巡礼風の旅人に貫重な財産の馬を貸そうものだろう。曽良の随行日記にもこのエピソードは書かれていない。だからといって芭蕉のつくり話だといってしまうには、あまりにも自然な物語である。
「かさねとは…」の句は、曽良の句集「雪まるげ」や曽良関係の資料にはまったくでていない。ただ「おくの細道」だけにでてくるのである。そのことを理由として、これは芭蕉の代作であると多くの研究者がいっている。これは重箱の隅をつっつくような話で、私たちはこのエピソードを味わえばよいのだ。
かさねという名の小さな女の子が、馬を追って懸命に駆けてくる。もう一人の子とかさねとは、芭蕉と曽良を草の中の迷宮から救い出そうとしている馬と一体のものなのだ。ここには救いのイメージが濃密に漂っている。
芭蕉が「おくの細道」の旅にでたのは、数えで四十六歳の時だ。人生歳は晩年である。実際、芭蕉はその五年後に五十一歳で死んでいる。四十六歳の芭蕉は、すでに老成した大家である。短命だということが、人を早く成熟させたのだ。人生八十年以上となつた今日では、人はいつまでも成熟せず、死ぬ頃になっても頼りない。長命であろうと短命であろうと、人が一生のうちにできることは同じだという気がするのである。
その大家がすべてを捨て、捨身して旅にでたのである。旅とは、捨てることなのだ。捨てて、言葉の表現者として完成しようとした。晩年に江戸で俳諧の宗匠であった芭蕉は、そこにいれば俳諧の大家としてみんなに尊重され、生活に困ることもない。しかしながら、表現者としては、とてもそんなことで満足することはできなかったのだ。つまり芭蕉はすべてを捨てて旅をすることによつて、表現者として生まれ変わりたかったのである。
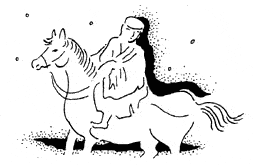 「おくの細道」の旅は元禄二年三月にはじまった。元禄と年号が変わったのは半年前の前年九月で、これから金銭がものをいう時代になっていく。江戸で支配階級の武士や、富を支配していた大商人たちに俳諧という風流の道を教えていた芭蕉は、時代の変わり方を一早く認識し、そんな世界から逃がれるためにすべてを捨てて旅にでたのである。 「おくの細道」の旅は元禄二年三月にはじまった。元禄と年号が変わったのは半年前の前年九月で、これから金銭がものをいう時代になっていく。江戸で支配階級の武士や、富を支配していた大商人たちに俳諧という風流の道を教えていた芭蕉は、時代の変わり方を一早く認識し、そんな世界から逃がれるためにすべてを捨てて旅にでたのである。
つまり、芭蕉は旅にでてもまだ迷っていたのである。そこに無垢な童子、天使のようなかさねが現われ、迷っている芭蕉を導いていく。なんと美しいエピソードであろうか。救いのイメージが、ここには鮮明に描かれている。フィクションとかノンフィクションとかの憶測は、どうでもよいことである。
黒羽を過ぎて、芭蕉は本当に生まれ変わるべき空間を求めて「みちのく」へと旅立っていく。その前に、芭蕉はどうしても救われていなければならなかったのである。
|
|
|