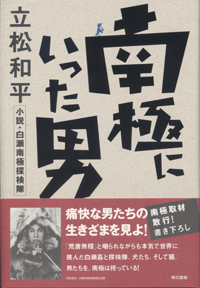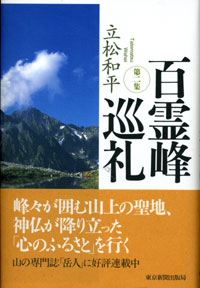|
あとがき
国立極地研究所の招きで私が南極を訪れたのは、平成十九(二〇〇七)年一月のことである。自己犠牲もいとわない先人の献身的な努力の結果、昭和基地はまことに快適な研究空間になり、居住空間となっていた。窓の外に氷の海とそこに浮かぶ氷山を眺めた時、沈まない太陽のもとで光が時々刻々と変化する風景は、禅味を帯びた枯山水を思わせ、私は南極山水と私の中だけで命名した。もちろん一般的な通り名ではないが、それほどに精神性を感じさせたのだ。なにより、予想していなかったことだったが、南極の風景はただ非常に美しかった。
今回の南極への旅にさいし、以前から企図していた小説が頭にあった。明治四十三(一九一〇)年、わずか二百四トンの木造帆船開南丸で南極探検を決行した白瀬矗たち探検隊の物語である。彼らの胆力が私たちの時代から失われて久しい。南極の氷河や氷海などを南極観測船「しらせ」搭載のヘリコプターで案内してもらい、その風景から刺激されて浮かんだ言葉をメモし、写真に撮り、南極山水にしみじみと触れ、取材を重ねるうち、百年前に現代とはくらべものにならない貧弱な装備で南極に立ち向かった白瀬南極探検隊の小説が実感をもって迫ってきた。
昭和基地の図書室では、かねてより入手を希望していた白瀬南極探検隊の公式記録である『南極記』が目にとまった。大隈重信が序文を書いて南極探検後援会が編纂し、大正二年十二月十五日に刊行され、昭和五十九年九月四日に白瀬南極探検隊を偲ぶ会によって復刻された部厚い本である。この本は昭和基地にしかないものだという思いが私にはあり、ミスプリントの用紙がたくさんあったのでその裏側にコピーをさせてもらった。気合をいれてコピーをしていると、神山孝吉越冬隊長がきておっしゃった。
「あと何部かあるから、持っていっていいですよ」
白瀬矗の故郷である秋田県にかほ市(旧金浦(このうら)町)の白瀬南極探検隊記念館からは、当時の写真を含め、貴重な資料の提供をいただいた。金浦にいくと、白瀬は今でも生きているかのように尊敬を集めていた。
とくに今回、白瀬氏と探検隊のご遺族のかたがたにはひとかたならぬご理解とご支援、そして思いもおよばぬ貴重なアドバイスをいただいた。白瀬知和さん、白瀬ゆりさん、『南極探検日記』『南極探検私録』の著者多田恵一氏のご遺族、多田キミ子さん、横地美農里さんである。小説を書こうと発願した私に、たちまち数々の支援が寄せられたのは、白瀬南極探検隊が人の心の中に今も生きているからである。
本文中のさまざまな挿話、たとえば猫を連れていった人がいたり、釣竿でアポウドリを釣ったこと、「赤道」を見る話や船の上の餅つき、海賊船騒ぎなどの愉快な話も、すべて白瀬本人の著作や『南極記』、多田恵一氏の記録などに残された事実をもとにしている。白瀬南極探検隊の旅は、命を賭けた冒険であり、一見、悲壮感のみがただようように受け取られがちであるが、それだけではなかったようだ。
今回の仕事も、前回の『道元禅師』と同じく東京書籍の小島岳彦氏と組んだからこそ、こうしてなし得たのである。小島氏の熱心な叱咤激励と協力に感謝する。
二〇〇八年盛夏 異常ともいうべき猛暑の東京にて
|