|
マラッカはスマトラ島との間にあるマラッカ海峡に面した古都である。このマラッカ海峡を通らなければ、スマトラ島とジャワ島を大回りしなければならない。経済効率とは時間と経費のことで、マラッカ海峡を通れば経済効率はよくなる。もしここを通らなければ効率はぐんと落ちる。
かくしてマラッカ海峡には、大型貨物船や大型タンカーがひしめくことになる。実際に海岸で海を眺めていると、巨大な船が幾艘も蜃気楼のように通っていく。もし何らかの事情でマラッカ海峡が封鎖されたとしたら、日本などの東アジアの国々はパニックになるだろう。石油なども充分に届かなくなる。
マレー半島では、インド洋例の海岸は泥で濁っている。山の樹木を伐採し、開発をしすぎて、泥が海に流れ込んでいる。水は泥色に濁っていて、砂浜のかわりに泥の浜がある。どうしてこんなに汚れてしまったのだろうかと思う。この泥海にもかかわらず、海岸にリゾートホテルなども建設されているようだ。マレー半島の反対側の南シナ海側は、海に泥が流れ込まず、砂浜は美しい。
私は二十年前、このマラッカにやってきた。宇都宮市役所に五年九カ月勤め、小説を書いて生きていきたいとの思いが絶ちがたく、辞離した。金はなかったがあり余る時間ができたので、行方知れずになるような昔の旅が忘れられず、シンガポール、マレーシア、インドネシアあたりを旅した。それから二十年たって、再びシンガポールとマレーシアにやってきたのであった。
その旅の中で、マラッカが最も印象的であった。赤レンガの建物がならび、世界につながっている港の香りがあった。海洋文化の風情が街のあっちこつちにあり、長い歴史によって形づくられた雰囲気があった。
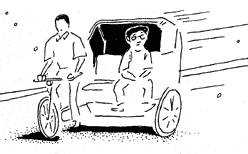 長い軒廊のある通りを、私は人力車に乗って遊んだのであった。人力車の運ちゃんは親切で、私が一番好感を持ったのはこの街を愛しているということだった。どこにいくというあてもなかったから、半日ほど雇ってゆっくりとあっちにいったりこっちにいったりした。自転車をこぐ速度以上にはでないので、微風が吹くほどの速さは気持ちがよかった。 長い軒廊のある通りを、私は人力車に乗って遊んだのであった。人力車の運ちゃんは親切で、私が一番好感を持ったのはこの街を愛しているということだった。どこにいくというあてもなかったから、半日ほど雇ってゆっくりとあっちにいったりこっちにいったりした。自転車をこぐ速度以上にはでないので、微風が吹くほどの速さは気持ちがよかった。
サンチャゴ砦は市内で随一の観光スポットである。石積みの建築に大砲を設置したサンチャゴ砦は、一五一一年ポオランダとの戦争にそなえてポルトガル軍によって築かれた。マレーシアはポルトガル、オランダ、イギリスによって、四百五十年近く支配されてきた。
海からやってくる艦船に向かって大砲を射ったサンチャゴ砦は、当然海に面していた。二十年前の私の記憶も、裏の小高い丘に登ればすぐ前は海だったのだが、今は芝生の広場があり、その向こうにレストラン街やら高層ホテルが建てられ、まだその先までも陸地はつづいて住宅などが建てられている。つまり、海が埋め立てられたのだ。
チャイナタウンのトゥン・タン・チェン・ロック通りは、日差しをさえぎる軒廊がつづき、熱帯を旅するものには心やさしいところだ。マレー風と中国風が融合した建物は、まことに優美である。しかし一方通行で自転車がひっきりなしに通り、騒音も排気ガスもひどくて、向こう側に渡るのも困離だ。それなのに、これらの建物は土産物屋や骨董品屋かレストランかホテルか、いずれにせよ観光客向けの商売をしている。観光客は世界中から集まってくるのだから、歩行者優先の道路にすればいかがかと思う。
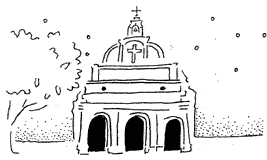 それにしても不思議な街である。数百年前にマレーシアに移住してきた中国人をパパといい、彼らと結塘したマレー系の女性をニョニヤと呼ぷ。建設、家具などに独特の文化を育てた。ことにニョニャ料理は、中華料理とマレー料理とが融合したも それにしても不思議な街である。数百年前にマレーシアに移住してきた中国人をパパといい、彼らと結塘したマレー系の女性をニョニヤと呼ぷ。建設、家具などに独特の文化を育てた。ことにニョニャ料理は、中華料理とマレー料理とが融合したも
ので、どちらの風格も失っていない。
ニョニヤの精神性が感じられていいものである。昼食には、ニョニヤ料理を食した。
二十年前の記憶では、この通りの向こう側は海岸であった。青い波が赤レンガの建物に寄せて、風情があった。あの記憶は錯覚だったのかと思えるほどに、街は変わっていた。
埋め立てられて、海は遥か彼方に去り、見えない。マラッカの古都としての風格は、著しくそこなわれてしまった。
マラッカ川のほとりに、赤く塗られたカマポコ型のオランダ教会が建っている。まわりには土産物屋が並んでいるが、昔から変わらないのはこの川のまわりの風景かもしれない。
川の水は腐ってすえた臭いがしている。その水に浮かんだ船が、丸太を積んでは出港していく。傍らに結ってある観光船を、黒い波が洗う。また新たな荷船がやってきて接岸し、クレーンがうなって人が動きだし、丸太が積まれていく。
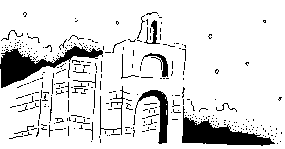 世界中の港から船が集まってきたマラッカ港は消滅し、どこか郊外に新港がつくられていることだろう。旅情などを求めるのは、旅人の勝手な感傷だ。街は生きて動いているのだが、この時代を支配している経済効率の原理は、街の潤いなと計測できないものを確実に滅ぼしていく。 世界中の港から船が集まってきたマラッカ港は消滅し、どこか郊外に新港がつくられていることだろう。旅情などを求めるのは、旅人の勝手な感傷だ。街は生きて動いているのだが、この時代を支配している経済効率の原理は、街の潤いなと計測できないものを確実に滅ぼしていく。
マラッカ川の港のはずれ、茫漠とした砂漠のような埋立て地がはじまるあたりに、近隣の港にいく連絡船の船着場がある。大荷物を持った人、物売り、タクシーや人力車の客ひきでにぎわいなど、昔ながらの雰囲気があった。人の生活の臭いがあるところがよい。変わっていないことに、ほっとする。
夜、郊外にあるポルトガル村に食事にいった。ポルトガル人の子孫たちの村で、たいていポルトガル姓を持ち、カトリック教徒ということである。海に張り出したシーフードレストランで、チリークラブを食べた。こればかりは変わらない。
|
|